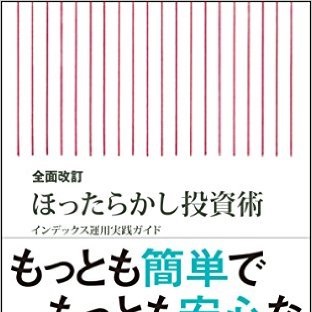毎日忙しい人でもできる投資の方法を、人気経済評論家の山崎元氏が教えます。インデックス投資ブログで有名な、水瀬ケンイチ氏の実践的なアドバイスもあります。
おすすめ
★★★★★☆☆☆☆☆
対象読者層
なるべく手間をかけずに、投資で成果を上げたい人。
インデックス投資マニア。
難易度は初級者以上。入門書とは言えない。
要約と注目ポイント
手間のかからない、簡単で無難で負けにくいお金の運用法を、前著「ほったらかし投資術」で提示した。4年経ち、環境変化もふまえて全面改訂したが、投資の基本姿勢に変わりはない。
投資はインデックス運用で行う。
インデックス投資がおすすめな理由
インデックス運用の利点は、
①手数料コストが安い。
②シンプルでわかりやすい。
(資産の価値が指数でわかるので、理解しやすい。ポートフォリオが管理しやすい。)
③負けにくく無難である。
(インデックスファンドは過半のアクティブファンドに勝つ。そして、勝てるアクティブファンドを事前に知ることはできない。)
インデックス投資ブロガー水瀬氏の投資体験談
将来のため資産をつくろうと投資を開始。ファンダメンタルやテクニカルの分析に、時間と労力を費やして株を買う。
精神的にも疲れるが、それほど努力しても儲からない。市場全体の下落にも巻き込まれる。
そんなときにインデックス投資を知って始める。自分の性格にも合い、継続できた。12年続けたら、良い結果が出ている。
個人がお金を運用する正しい手順
①家計の状態を把握する。
②資産配分を考える。
③個々のアセットクラスに、どの運用商品がベストか考える。
④どの金融機関で投資するか選ぶ。
⑤DC(確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)が使えるなら、③と④のところで組み込む。
⑥ときどきモニタリングとメンテナンスをする。
資産運用の簡単な方法
①非常用生活費と運用資金を分ける。
②ネット証券に口座開設。
③リスク資産の投資額決定。
④リスク資産に配分したお金で、国内株式(MAXISトピックス上場投信)50%と外国株式(ニッセイ外国株式インデックスファンド)50%を買う。
⑤DCとNISAから先にリスク資産を割り振る。
⑥運用以外のお金は、個人向け国債変動金利10年型か預金、MRFで保有する。
⑦モニタリングとメンテナンスをする。
⑧お金が必要になったら、必要な分だけリスク資産を売却する。
投資対象の資産の解説
アセットアロケーションは、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、現金の5つが基本となる。
ただし現在、先進国は歴史的低金利なので、国内債券を持つ意味はほとんどない。国内債券は現金で良い。外国債券も為替リスクがある上、金利の低下余地は小さいので保有しない。
結果、国内株式と外国株式と現金を適切な比率で持つことにする。
資産運用の各手順を説明
非常用の生活費はいくら必要か
ネット証券の選び方
口座開設の仕方
DCとNISAの説明
リスク資産に投資する額の決め方
積み立て投資と一括投資について
国内株式と外国株式の比率
インデックスファンドの銘柄選択
無リスク資産について
モニタリングとリバランス
などなど‥‥
そのほか、投資の勉強になるトピックなど
インデックス投資を学べる本、サイトの紹介など。
おすすめのインデックスファンド、ETF銘柄の解説。
ETFマネジャーへのインタビュー。
書評
前著の「ほったらかし投資術」や、山崎元氏の「全面改訂 超簡単 お金の運用術」などを読んでいると、運用方法に違いはほとんどありません。投資の考え方も同じなので(当然ですが)、どれかを読んでいれば十分だろうと思います。
正しい投資の方法は簡単です。一部に非常用の生活費を残し、最大損失を想定してそれに耐えられる範囲で、日本と外国のコストの低い株式インデックスファンドを買う。積み立て続ける。持ち続ける。終わり。
インデックス投資の優位性や、それを実現する手法も書かれています。ですので、この本1冊ですべて済むはずなのですが、なかなかそうでもないように思われます。
インデックス投資は凄い、保有し続けることは威力がある。これらは、自分なりに投資を勉強して、下手くそなアクティブ投資を実行したあとに、身に染みてわかるものだからです。
結局、ある程度は自分で投資の本などを読み、投資経験を持たないと、インデックス投資に移行しないと思います。
前著から新しくなったところは、DCとNISAの解説および活用法が加わったことです。あともう1点は、債券についてです。先進国の金利低下が極まったので、国内債券に投資する必要は特にない、と述べています。これには私も同感です。
本書の特徴のひとつに、ファンドマネジャーへのインタビューがあります。今回もありまして、ETFマネジャーです。興味のある方はどうぞ。
まとめると、前著や山崎元氏の著作を読んでいる人は、特に読む必要はありません。付け足すのは、確定拠出年金やNISAの知識をアップデートすることと、低金利が今後どうなるかに注意することです。
本書は、投資に興味がない一般人に、手間のかからない合理的な運用方法を教えることを目的にしています。しかし、それにしては難易度が高過ぎます。
著者たちには物足りないでしょうが、投資の基本や運用方法をもっとやさしく説明しないと、一般人には理解できません。実質的には、本書はインデックス投資マニアのための本です。
(書評2015/06/21)