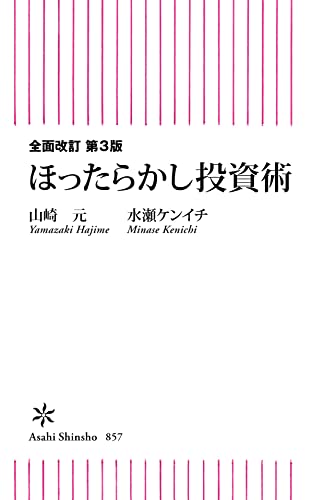投資に時間や労力をかけずに、ベストに近い運用成績を得よう。人気経済評論家の山崎元氏と、有名インデックス投資ブロガーの水瀬ケンイチ氏が教える、ほったらかしでできる投資術です。
おすすめ
★★★★★★☆☆☆☆
対象読者層
人生の終わりまでを見すえた長期投資を、時間や労力をかけずに行いたい一般人。
あるいは、インデックス投資マニア。
難易度は初級者以上。入門書とは言えない。
要約と注目ポイント
著者らは、普通の人でもできる手間のかからない、簡単で無難で負けにくいお金の運用法を考えてきた。
それは、2010年に出版された「ほったらかし投資術」と、2015年に出版された「全面改訂 ほったらかし投資術」で提示した。
2022年になり投資をする環境がまた変化してきたが、ここで最も簡単にできる「ほったらかし投資」の公式本をつくろうと考え第3版を書いた。
「ほったらかし投資術」とは、機関投資家のようなプロに近い運用成績が期待できて、個人でも簡単にできる資産運用の具体的な方法論だ。
ほったらかし投資は、インデックスファンドを使う。
インデックス投資ブロガーの体験から
約20年インデックスファンドに投資を続けたブロガー水瀬氏の体験から。
・20年のインデックスファンドへの積立投資で約1億円の資産を築けた。(年率6%程度の収益率)
・資産をつくると経済的に独立し、人生において自由な選択ができる。
・個別株投資に熱中していた時期は、時間もお金も浪費していた。インデックス運用に切り替えることによって、人生に余裕が生まれた。
・インデックス投資のいいところは、誰でも簡単に同じ運用ができること。
ほったらかし投資の実践法
1、3~6ヵ月分の生活費を普通預金に確保する。それ以外のお金は運用資金。
2、運用資金の中から、実際に投資する金額を決める。(1年で3分の1ほど価格が下落するリスクを受容できる金額)
投資対象は、全世界の株式に投資する低コストなインデックスファンド。
3、投資では、(NISAやiDeCoなど)税制上有利な運用口座を利用する。
4、投資しない運用資金は、銀行預金か個人向け国債変動金利型10年満期にする。
投資のポイント
・損失の可能性のある株式などは、短期国債のように損失のおそれがない無リスク資産より高いリターン(リスク・プレミアム)が得られる。
・若い人も高齢者も、最大損失を想定しておけばリスクを大きめにとってかまわない。
・投資すべき全世界株式インデックスファンドは、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)。もしくはそれに類似するもの。
・「個人向け国債変動金利型10年満期」の優位性や、銀行預金のペイオフなどの説明。
・NISAやiDeCoの具体的な説明。
・投資の三原則は、長期・分散・低コスト。ずっと長期で保有し続けること。広く世界の株式に分散投資すること。手数料の低いインデックスファンドやETFを選ぶこと。
・投資すべきインデックスファンドの具体例。
手数料の目安は、年率0.25%未満(低コスト)。純資産が少なすぎないこと(100億円以上)。インデックスとの乖離が小さいこと。
インデックスファンドは、全世界株式(日本含む)、全世界株式(日本除く)、先進国株式から選ぶ。
・投資するにはネット証券がおすすめ。(楽天、SBI、マネックスの解説)
・インデックス運用の説明。インデックス運用の優位性の解説。
・割引率とリスク・プレミアムの解説。リスクを引き受けてリターンを得るのだから、高成長の国や企業でも、低成長の国や企業でも、同じように投資はできる。
・そのほか、質疑応答。バンガードに勤務していた方のインタビュー。
書評
本書は第3版ですが、投資に関する考え方は変わっていないので、前著からブレはありません。ただし、投資対象に選ぶインデックスファンドを1つだけにすると言う方針転換があったので、表面上はやり方が変わっています。
前の著作から7年経って、けっこう投資の環境も社会も変わりましたので、知識のアップデートという意味で、読むと勉強になります。
ほったらかし投資は簡単です。非常用の生活費として預金を一部残し、それ以外を運用資金にする。最大損失を想定してそれに耐えられる範囲で、コストの低い全世界株式インデックスファンドを買う。積み立て続ける。持ち続ける。終わり。
ということで、投資術は簡単なのですが、なぜそうするのかを自分で納得するのはなかなか難しいです。
この本は投資初心者向けであり、投資に時間と労力をかけたくない人のための本です。しかし、なぜこのように投資するのかと自分で理解するには、もっと易しい入門書を何冊か読まないと無理です。
そういうわけで、この本の実践法に従い投資することは私も正しいと思いますが、やはり誰でも納得して投資したいので、投資に対する勉強は必要です。
この本は読む価値があると言えますが、初心者の方は、もっと易しい本をとりあえず4~5冊は読んでからじっくり読み込んでみるといいでしょう。
(書評2022/07/23)