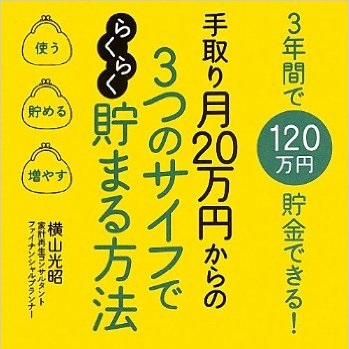手取り20万円でも、3年で120万円貯められる方法を教えます。
おすすめ
★★★★★★☆☆☆☆
対象読者層
家計が苦しい人。
お金の知識がゼロの人。
要約と注目ポイント
お金を貯めるためには、3つのサイフを持つ。ここでいうサイフとは、口座のこと。
①生活費を入れる口座(使うサイフ)
②貯蓄の口座(貯めるサイフ)
③資産運用の口座(増やすサイフ)
3つの口座に分けて管理すると、お金は貯められる。
はじめに「使うサイフ」を貯め、次に「貯めるサイフ」に貯めて、最後に「増やすサイフ」に取りかかる。順番を守ること。
お金持ちとは、お金に悩まずに生きていける人。3つのサイフがあれば、あなたもお金持ちになれる。
お金を貯められるかは、基本的なことをきちんとできるかにかかっている。
3つのサイフを始める前の準備
家計の支出を、固定費と変動費に分けてみる。
①固定費(住居費、保険料、小遣いなど)から削減していく。
まず生命保険料を見直す。
子供が生まれたとき、少額の負担でかけられる、収入保障保険である死亡保障だけ必要だ。医療保障(がん保険)は、自分の事情に合わせて検討する。
賃貸に住んでいるなら、家賃の安い部屋への引越しを検討する。
携帯電話や固定電話、インターネット接続のプランを見直し、通信費を削る。
自由に使える小遣いは、手取り月収の7%まで。
国民年金は払いましょう。
住宅ローンがあるなら、借り換えで少なくできるか調べる。「貯めるサイフ」が貯まり余裕があるなら、繰り上げ返済も考える。
②変動費は、消費、浪費、投資に区別して、不要な支出を減らす。
お金を使うときに、消費か浪費か投資か、自問してみる。
浪費の部分を自分で見つけ、削減していく。家計簿をつけたり、レシートを残したりして、自分の浪費の習慣を見える化し、生活を改善する。
消費、浪費、投資の理想の比率は、
消費70%
浪費5%
投資25%(内訳は、貯金などの金融投資:手取り月収の6分の1である16.7%、自己啓発などの自己投資:8.3%)
となる。
使うサイフ
「使うサイフ」は、常に手取り月収の半分が入っている状態にする。
毎月、手取り月収の10%を残していき、手取り月収の半分まで「使うサイフ」に貯める。(5か月で貯まる。)急な出費をカバーするのが目的。
「使うサイフ」で大切なこと
赤字の家計は、必ず黒字にする。
イレギュラーな支出があっても、イレギュラーな節約で埋める。
月の生活費を5等分し、1か月を5週間と考え、1週ごとにお金を管理する。
買い物は週に2~3回まで。
クレジットカードはなるべく使わない。買い物依存症の人は、デビットカードを利用しよう。
収入が少し増えても、生活レベルは変えないこと。
お金を使わなくても、楽しく暮らす方法はある。
貯めるサイフ
毎月、手取り月収の6分の1を残し、手取り月収の6か月分を「貯めるサイフ」に貯める。(3年で貯まる。)生活防衛資金であり、病気や失業に備えるのが目的。
「貯めるサイフ」で大切なこと
給料が入ったら、はじめに6分の1を先取りして天引きする方法がある。
「貯めるサイフ」が貯まったら、旅行などの目的別貯金をしてもよい。
子供の教育費は、必要額を計算し、長期的に目的別貯金として貯めていく。
住宅の購入は慎重に。買うなら、頭金として物件価格の2割は用意する。
ボーナスの7割は、「貯めるサイフ」や「増やすサイフ」に入れる。3割は自由に使ってよい。
増やすサイフ
「貯めるサイフ」に手取り月収6か月分が貯まったあとに、「増やすサイフ」にお金を入れていく。毎月、手取り月収の6分の1を残して、「増やすサイフ」に入金する。
長期分散投資をして、安定的に増やすのが目的(インフレ対策)。
「増やすサイフ」で大切なこと。
投資では、金融投資でお金を増やすことと、自己投資で自分を育てることを考える。
金融投資である「増やすサイフ」は、証券会社の口座でつくる。
長期的に、毎月こつこつ積み立て購入で、分散投資をしていく。
英語、IT、ファイナンスのスキルを学び、人脈を広げ、自分の器を大きくするなど、自己投資も大切だ。
書評
非正規雇用が労働者の4割となり、自分の生活や人生を、会社に頼れない時代です。お金の知識を身につけ、身を守れる額の貯金をつくることは大切です。
家計が常に苦しい、お金を貯める方法がわからない、という人に本書をおすすめできます。
お金の相談に来た人の生活を見直し、行動を改善させ貯金できる体質に変えるのが、著者の真骨頂という印象です。
以前に、同じ著者の「年収200万円からの貯金生活宣言」を紹介しました。「年収200万円からの貯金生活宣言」でも、アドバイスは似ていました。
横山氏は著作がとても多いので、どれを読めばいいのかよくわかりませんが、貯金に対するアプローチは一貫しています。
自分の生活をしっかり見つめ直し、貯金ができる行動様式を身につけさせるのが得意なのだと思います。
大げさに言うと、人生に規律を持たせて、目標に向かって一歩ずつ努力させるように仕向けるわけです。その目標が貯金であり、その延長として自己投資での自分の成長です。
生活を見直し、不要な支出を減らす。日常の急な出費に備えた貯金、そして病気や失業に耐えるための生活防衛資金をつくる。そのあとから長期投資として、積み立てで投資信託を買っていく。
実に王道で真っ当な方法と感じました。
著者が最も得意なのは、生活の見直しで貯金できる体質にするところだと思います。純粋な金融投資については、もっと突き詰められると思います。
バランス型ファンドよりは、手数料のさらに安い、グローバル株式ファンドとトピックス連動型ファンドを組み合わせるとか。
ただ、お金知識ゼロの人を読者に想定しているので、そこまで要求するのは酷でもあります。
あと付け加えるとすれば、本文の解説で、株式と債券を両方持てば資産運用が安定するとしているのは、修正の余地がありそうです。
本書の出版が2013年9月なので、こちらもそこまで求めるのは厳しいかもしれませんが、現在、債券を買う意味はほとんどないと私は考えます。
先進国すべてがゼロからマイナス金利なので、債券は値上がりの期待よりは、値下がりリスクの方が大きいと言えます。今の状況では、株式が暴落した局面で債券が値上がりするかは不明です。
今なら、債券を買う分のお金は、普通預金で十分と思います。その普通預金は、経済状況が変わってきてから運用を考えれば良いでしょう。
(書評2015/11/08)