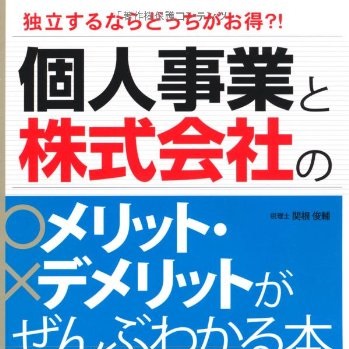独立するときは、個人事業にするか会社を設立するか迷います。堅実に小さく始めたいなら個人事業。自信があり最初から大きくいくなら会社設立。個人事業と会社設立のメリット・デメリットを、しっかりまとめています。
おすすめ
★★★★★★☆☆☆☆
対象読者層
起業したい人。
要約と注目ポイント
独立の前に、起業の動機、会社を辞めるメリット・デメリット、準備の状況などをよく考えること。可能なら、会社勤めをしながら副業で始めてみる。
独立前の準備
事業計画を考える。
事業の概要、起業の動機、経営理念、市場分析、ビジネスプラン、中長期の展望。
資金計画を考える。
毎月の生活費、事業の固定費、事業の変動費を算出する。そこから損益分岐点売上高を計算する。必要な開業資金を計算する。
個人事業について
名称は屋号。
個人事業の場合、資金の出し入れに制約は少ない。
開業手続きは簡単で、費用はかからない。
交際費は無制限。自宅は業務用の面積分を経費にできる。
青色申告にすべし。決算や申告の作業は会社より楽。
事業内容を変更しやすい。廃業するのも簡単。
株式会社について
名称は商号。
会社の資本金は、私用では出し入れできない。
設立するのに事務手続きが多く、お金も25万円は必要。
交際費は600万円まで。自宅を社宅にすることも可能。社内規定をつくれば、出張手当や慶弔費も経費になる。
車、生命保険料、退職金などは会社の方が節税しやすい。
複式簿記が必須。決算では損益計算書と賃借対照表を提出し、納税期限は早い。
会社法に則って運営し、議事録を残すこと。事業の売買や継承がやりやすい。
個人事業主の税金、会社経営者の税金
個人事業主の税金
個人事業では、
事業所得 = 売上 ― 必要経費
となり、事業所得に個人の所得税や住民税がかかる。
個人事業では、家族に給与を払うと、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けられない。
会社経営者の税金
会社では、
会社の利益 = 売上 ― 経費(役員報酬を含む)
となり、会社の利益に法人税がかかる。
役員報酬に個人の所得税や住民税がかかる。
給与所得控除の部分で、会社をつくると税金が少なくなる場合がある。
家族にも給与を払うと、税金が少なくなる。年収が多い人は、会社をつくって家族に給与を払うと効果的。
節税の知識
前々年の課税売上高が1000万円以下ならば、消費税の納税義務が免除される。個人事業から始めて会社をつくった方が、免税期間を長くできる場合がある。
会社は赤字でも、法人住民税を払う。個人事業は3年、会社は9年、赤字を繰り越せる。
事業用の不動産は会社で売買した方がよいが、マイホームは住宅ローンの優遇措置があるので個人で売買した方がよい。
経営セーフティ共済と小規模企業共済は、節税に使える。
個人事業と会社の比較
個人事業より会社の方が信用され、資金調達もしやすい。従業員の採用も会社が有利。出資や利益の配分、意思決定も会社の方が明確。
個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入。社長は、健康保険と厚生年金保険に入る。健康保険の方が負担は重いが、傷病手当金や出産手当金のメリットはある。
個人事業でも会社でも、従業員を雇ったら雇用保険と労災保険の加入義務がある。雇用保険に加入しないと、ほとんどの助成金は受けられない。
個人事業と会社設立の比較チェックリストつき。
個人事業を始めるには
届出と手続き、法人成りの解説。
会社をつくるには
会社の種類、定款の作成、登記、届出と手続きなどの解説。
書評
図表が多く、説明の文章もわかりやすくて読みやすいです。ただ、はじめからきっちり解説していきます。
今まで税金に関心がなく、一度も確定申告をしたことがない、といった人は、やさしめの税金の本や起業の本を他にも読んだ方がよいかと思います。
類書に書かれているような基本事項は押さえてあるので、読んであらためて勉強になりました。個人事業と株式会社を比較する本ですが、起業したいとか副業を始めてみた、といった人にもお勧めできる本です。
ところで、税金や社会保険料は延滞しないように、借り入れをしてでも払うべきとコラムにありました。延滞税は14.6%で、免除の可能性もほとんどないとのことです。このゼロ金利の時代に恐ろしい。
別の本でも、社会保険料の重い負担に耐えられず、倒産する会社が多いと書かれていました。日本は財政が非常に悪化していますが、小手先の対策として社会保険料の負担をどんどん上げています。
会社にとっても、従業員の保険料を負担することはかなり重要な問題となっています。社員の年金とか健康保険とか。社会状況で税制などが変わってくるので、日頃から社会的関心は広く持っておくべきですね。
(書評2015/04/25)