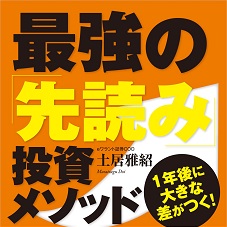中央銀行がつくりだした金融緩和バブルも、そろそろ危ない。著者によれば、2016~2017年にかけて破裂の恐れがあります。バブル崩壊に備えた投資法を教えます。
おすすめ
★★★★★★☆☆☆☆
対象読者層
世界経済に興味のある人。
投資をしたいが、暴落には巻き込まれたくない人。
要約と注目ポイント
バブルの基礎知識
金融市場では、10年に1回くらいバブルが発生して崩壊する。近年はグローバル化のため、世界のあらゆる市場で同時に暴落が起きる傾向がある。
ITバブルのようにブームが限定されていたり、バブルが株式市場にとどまれば、参加者は少ない。不動産でもバブルが発生すれば、一般人の多くが巻き込まれ、社会的影響は大きい。
アベノミクスは、世界中で行われている量的緩和バブルの一部である。バフェット指標で見れば米国株はバブルの領域で、日本株も高い水準にある。
サブプライムバブルの株価のピークは2007年で、すでに8年経っている。中央銀行の量的緩和で生じた金余りバブルも、そろそろ破裂の可能性がある。
バブルの発生条件
①通貨が過剰に供給される。金融緩和でカネ余りとなる。
②前回のバブル崩壊から時間が経過した。バブルの痛い思いを忘れた。
③投機を正当化するもっともらしい理由がある。楽観的な夢を抱く。
バブル崩壊の原因となりそうな出来事
大本命はアメリカの利上げ。過去の例では、最初の利上げをして6カ月から2~3年で株価が下落に転じている。
その他
①中国不動産バブルの崩壊。
②日本の消費税再増税。
③中東情勢。
④原油安。
などなど‥‥
総合的に考えると、2016~2017年頃が危ない。
バブルの天井で避けるべき行動
①多額のローンでマイホームを買う。
②海外旅行。骨董品や美術品の購入。(不景気のときは安い。)
③節税目的の不動産投資。
などなど‥‥
バブルの天井でとるべき行動
①半年分の生活費と、投資用資金を貯める。
②割高な保険や金融商品を整理する。
③暴落時の投資候補を調べ、リストにする。購入予定の不動産や高額商品を下調べする。今は買わない。
などなど‥‥
バブル進行中の注意点
①プロ、専門家、専門機関、メディア、政府、すべての人が間違える。多数派の意見を鵜呑みにしない。混雑した投資対象には投資しない。
②株価の目標価格がどんどん上方修正される。前年のパフォーマンスがものすごく良い。(自分も含め)多くの人が儲け自慢をする。これらの現象があれば、危険な兆候。
などなど‥‥
バブルへの対処を含んだ10の投資法
以下の10の投資戦略から、自分に合うものを3つ併用する。併用することで、どのような経済環境になってもパフォーマンスが安定する。
リターンを狙う積極的な5つの投資法
①日本株と米国株(のETF)を、10月末に買い、4月末に売る。
②バフェット流に、暴落前に現金ポジションを多く持ち、暴落時に優良株や株価指数ETFを大量に買う。しかし、大底を見極めるのはとても難しい。S&P500が直近高値から30%を超えて下落し、S&P500のVIX指数の月中高値が45超となったあと、落ち着いて35まで下がったときを買いタイミングとする。
③トレンドに乗る、順張り投資。
などなど‥‥
守りを重視した5つの投資法
①10月末買い、4月末売りの手法に、トレーリングストップを加える。
②今後の生産年齢人口の伸び、若年層識字率、識字率の伸びしろを参考に、将来性のある国に長期投資する。フィリピン、メキシコ、アメリカ、インドネシア、インド、エジプト、ナイジェリア、バングラデシュなど。
③ゴールドへの投資。金ETF、金ミニ先物、金レバレッジトラッカーを買う。
などなど‥‥
そのほかの解説
NISA利用の注意点。
退職金を運用するときの注意点。
アベノミクス後の展望。
書評
前半では、世界経済の現状と、過去のバブル相場の特徴を解説しています。それをふまえて、バブル相場の暴落に巻き込まれないためにどうするか考察します。
後半では、繰り返されるバブル相場を考えたうえで、10の投資戦略を紹介します。さらに、NISA、退職金の運用、アベノミクスの今後といった、個別事項も取り上げます。
前半は、具体的なデータを揃え、グラフも豊富で、読みやすい解説となっています。内容に大きな驚きはないですが、簡潔に今の金融市場を復習できます。
リーマンショックを受け、各国の中央銀行が超金融緩和を行いました。危機はひとまず去りましたが、リスク資産の価格が相当割高になってきたので、そろそろ危ないです。アメリカの利上げが一番重要です。
後半の10の投資法ですが、詳細は本書をお読みください。10あれば、1つや2つは気に入る投資法もあるかと思います。
投資戦略が一本足打法だと、大失敗もあります。考え方の異なる投資戦略をいくつか用意し、運用を分散しておけば、パフォーマンスの安定化につながると思われます。自分に合う投資法があれば、取り入れてみるのも一案でしょう。
NISAについては、損益が相殺できないという最大の欠点をどう克服するか考えます。退職金の運用は、一言でまとめれば、浮かれていきなり全額を投資するなということです。
最後のアベノミクス後の展望ですが、これは私も一生懸命考えています。私の考えは、当局は金融抑圧政策を取る(緩いインフレを起こしながら長期金利を低く抑える)というものです。
安倍政権は、もう政府債務を返済する気がないと感じます。ゆっくりゆっくり、政府債務を預金者(国民)の資産と相殺していくのでしょう。
本書ではこれに関連し、デット・ジュビリー(Debt Jubilee)が説明されています。私は初めてこの言葉を聞きました。
中央銀行が、発行した通貨で国債を買い、その国債をバランスシート上の資産とします。その資産を通貨発行分の負債と相殺すると、債務が消えるというものです。その方法の変形として、中央銀行が国債を永久に保有するという手もあります。
そうすれば日本のGDP比243%、1000兆円の公的債務が消滅するのです。しかし、そんなことが本当に可能なのですか?
私の頭では、よくは理解できませんでした。このデット・ジュビリーの結末を、著者ははっきりとは書いていません。ですが、どうも円安(経常赤字の定着)で持続不可能になると示唆しているようです。
私も、通貨安が止まらなくなったときが金融抑圧政策の限界かなと、ぼんやり想像していました。財政ファイナンスと通貨高への介入は無限にできますが、通貨安への介入は限度があります。円安が止められなくなり、インフレが制御できなくなれば、アベノミクスの終わりかと考えさせられました。
(書評2015/07/26)