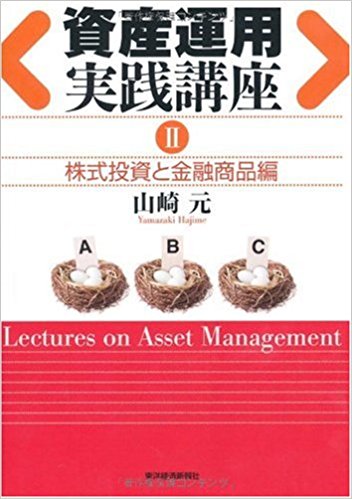前回紹介した「資産運用実践講座Ⅰ 投資理論と運用計画編」の続きです。上下巻の下巻にあたります。
おすすめ
★★★★★★★★☆☆
対象読者層
正しい資産運用について勉強したい人。難易度は初級者から中級者あたりが適当です。
要約
株式投資
・株式のリターンが債券のリターンより長期で見て高いとは、必ずしも言えない。過去のデータ(特に外国のデータ)を引いて、リターンでは株式が債券を上回るとする主張が多い。しかし過去のデータから、今後も絶対に株式が有利と断言はできない。ただ株式投資は、大きなリスクをとって生産活動に資本を提供する行為なので、一般論として大きなリターンを期待することはできる。
・株式の理論価格は、
現在の理論株価 = 現在の1株利益 ÷(投資家の要求リターン - 利益成長率)
であり、変形して、
投資家の要求リターン = 益利回り + 利益成長率
名目金利 + リスクプレミアム = 益利回り + 利益成長率
となる。
すなわち、実質利益成長率が実質金利より高ければ株式投資は有利であり、実質利益成長率が実質金利より低ければ株式投資は不利である。インフレ初期は株式投資が有利となり、インフレ後期は株式投資が不利となる可能性がある。しかし投資家の予想と現実がずれることもあり、株式でインフレヘッジできるかはわからない。
・株式のリスクプレミアムは、直接測定することはできず、一致した学説もない。だいたい5~6%と考えられることが多かった。
・チャート分析だけで儲けることはできないと考えるのが、学術研究と運用業界の主流である。チャート分析が有効であると考えて頻回に取引することは、個人投資家にとって弊害がある。
・証券会社のアナリストの投資判断が、リターンを改善することはないだろう。
・株価は、将来の利益を予想して形成される。利益予想の変化が株価に影響を与えるので、決算情報や、会社四季報などの業績予想の推移を調べることは有意義である。1回目の上方修正の段階では株価は割安(買い)で、3~4回上方修正が続くと株価は割高(売り)となっていることが多い。
・PER、PBR、ROE、日経平均株価、TOPIXについて。
・個別銘柄に投資する場合は、業績予想の変化(推移)はどうなっているか、株価は割安か割高か、流動性など取引の状況はどうか、を確認する。損失が許容できる範囲の金額で、業種の異なる3銘柄以上に分散投資を心掛けるのがよい。
・時間を分散して株式を売買することに意味はない。取引回数が増えコストがかかることや、最適なポートフォリオをつくるのが遅れる機会損失がある。
・成長株投資について。
成長株投資で高いリターンを上げるには、他人より早く高成長に気付き、自分が株を買い終わったころに他人が高成長を知ることが必要である。これはなかなか難しい。また、成長株は期待外れ(成長鈍化など)になると、株価を大きく下げる。
・割安株投資について。
将来の利益の予測とPERから、またPBRから、割安か判断する。割安株は相対的に値動きが安定しており、銘柄選択基準もわかりやすいことから、割安株投資は個人投資家に向いている。
・イベントドリブンについて。
・株式を売却するときは、
①お金が必要になったとき。
②資産配分で、株式の比率が変わったとき。
③その銘柄のウェイトが大きくなり過ぎたとき。
④買った理由がなくなったとき。
・議決権行使について。
投資信託
・アクティブファンドは、市場平均に勝てない場合が多い。また、市場平均を上回る優良なアクティブファンドを、事前に見分けることはできない。手数料の差は、ファンドの優劣の大きな要因となる。
・パッシブファンドは、コストが低く個人投資家に適した金融商品だった。近年は、銘柄入れ替えなどに便乗する、コバンザメ投資や引値ギャランティといった現象が見られる。これらはパッシブファンドのリターンを低下させる。ただ現在でも、パッシブファンドはアクティブファンドより高いリターンを示す場合が多いので、パッシブファンドは優位性のある投資対象と考えられる。
・バランス型ファンドは、コストが高めで運用の中身が把握しにくいという欠点がある。ファンド・オブ・ファンズやライフサイクル型ファンドにも、同様の問題がある。本来は、投資家が資産配分を決定し、それぞれ適切な資産を組み合わせる方が望ましい。投資家自身が行うことで、コストが下がり、管理も容易となる。
・毎月分配型ファンドは、課税のタイミングが早くなるので損である。インカムゲインに対する心理的満足のほかに、長所はない。
・元本確保型商品は、投資家にとって利点はない。SRIファンドなどは投資の面で優位性はないので、投資家の価値観による。タクティカル・アセットアロケーションのシステム運用は、うまくいく時期といかない時期があり、また投資家がリスクの把握や管理をしにくくなるので勧められない。
・トップダウンとボトムアップについて。定量評価と定性評価について。
・シャープ・レシオとインフォメーション・レシオについて。
預金と債券
・利回りが確定している預金や債券では、運用期間と信用リスクの2面から考慮して、利回りを比較するのが原則である。このとき、利回りは複利で比較する。銀行預金の場合は、銀行の格付けも参考にできる。社債を個人投資家がリスク評価することは難しい。
・デフレで超低金利(ゼロ金利)の環境では、普通預金が安全で利便性もあるので良い。このような環境下では、運用期間や信用度に問題のある金融商品の利回りもゼロに近づくので、相対的に普通預金が優位となる。名目の利回りがゼロでも、普通預金が十分に有利である。
・金利が変化するときの金融商品の比較では、以下の点を考慮する。
①名目金利ではなく、インフレ率を考慮した実質金利で損得をはかる。
②長短の金利差を見て、得な方を選ぶ。
③今後の金利動向も考える。長期の債券では、金利上昇でキャピタルロスの可能性がある。
10年満期の変動金利個人向け国債は、運用リスクが小さく、検討してみる価値はある。手数料の高い外貨預金や外国債券は、常に不利である。
・銀行預金にもさまざまな種類があるが、どれだけの期間でいくらになって戻ってくるかを具体的に確認すること。外貨建てである、オプションが組み込まれている、対象者や期間が限られている、手数料の高い商品と抱き合わせである、などの問題がある場合もみられる。
・債券の解説。
①利回りが高くなれば、債券の価格は下がる。利回りが上がるということは、将来価値が不変ならば現在価値が下がるということである。
②インカムゲインとキャピタルゲインを両方合わせて、利回りを検討しなければならない。債券の期間が長いほど、価格が変動するリスクが大きくなる。
③利回りの比較は、複利で行う。
④デュレーションについて。
⑤債券の信用リスクは、格付け情報を参考にする。しかし個人投資家が債券の評価をするのは、極めて難しい。
・物価連動国債について。
その他の金融商品
・自分が理解できない金融商品は、購入してはならない。利益が出る仕組みや、売り手の取り分となる手数料、価格条件から見た損得などがわからないなら、理解できていない。
・為替レートについて(購買力平価、需給、資本取引)。
・外国株式、外国債券について。
その株式や債券がよい商品かと、その国の通貨がよいかは別々に考えるべきである。運用資産全体のうち、どの通貨をどれだけの比率で持つべきかを考える。外国の株式や債券でも、大半の為替リスクはヘッジできる。
・外国債券をどの通貨で運用しても、円建てでは円の金利と大きくは変わらない。基本的な期待リターンは自国通貨で運用した場合と同じだが、分散投資としての意味はある。
・外国株式では、金利や利益成長率、求められるリスクプレミアムの水準が日本と異なることに注意する。
・FXについて。
・先物、オプションについて。
・投機と投資とは。
書評
基本的には、1冊目と同じです。入門書のレベルは卒業した人が、もっと理論的に資産運用を独力で行うための本です。専門書まではいかない、中級者向けです。
これを通して読むと、投資の全範囲に目配りできるので本当に勉強になります。でも素人にはかなり難しいです。私も債券や為替のところは、厳しい箇所がありました。株式は興味があるので多少は勉強していて、本書もまあまあ理解できたのですが、債券と為替は勉強が必要です。
本書は合理的なので読むと納得するのですが、それでも他の良書とされる本と主張が異なる部分もあるので、投資とは方法論が確立していないものだと感じました。
「ウォール街のランダムウォーカー」や「敗者のゲーム」では、長期の株式パッシブ運用こそ最高と主張します。私も長期の株式投資が有利と思っています。しかし本書で、過去のデータをもとに絶対に将来も株式が債券を上回るとは言えないとか、パッシブファンドに及ぶ悪影響などを読むと、確かにそういう視点もあると気付きます。(ただし本書も株式を期待できる投資としています。)
最近は、先進国経済が長期に停滞するとも言われています。ヨーロッパでは景気後退、さらにはデフレの可能性が出てきました。これまで外国では長期の株式投資が報われてきましたが、日本では20年間、株式投資にいいところはありませんでした。もし今後、先進国経済が、あるいは世界経済が日本のように停滞するなら、株式投資にも疑問が湧いてきます。
そうすると、ただ株式をパッシブ運用するだけでは、賢い投資法ではないかもしれない(平均レベルは期待できますが)。ならばタイミングを見て、不況のときに株式を多く買い、好況のときに投資を抑えたくなります。でも景気の波を正確に認識するのは、極めて難しい。自分が景気の波を捉えられないなら、どうすべきか。そもそも市場のタイミングを見極めるのが無理だと考えるのが、パッシブ運用です。するとパッシブ運用に戻ります。今のところ、答えが見つかりません。
(書評2014/10/16)